
循環器内科
循環器内科
診療方針
市立四日市病院 循環器内科では、急性心筋梗塞や不安定狭心症、重症不整脈、急性心不全など生命に危険のある患者さんに、カテーテル治療を中心とした最新の高度医療を24時間体制で提供しています。特に急性心筋梗塞に対しては95%を超える症例に緊急カテーテル治療を行い、病院到着から90分以内に閉塞した冠動脈を再灌流する体制をめざしています。治療は心臓血管外科と連携し、治療ガイドラインに沿った安全で効率的な診療を心掛けています。
心房細動・発作性上室性頻拍などの不整脈に対するカテーテルアブレーション治療、左脚ブロックを伴う重症心不全に対する心臓再同期療法(CRT)、致死的不整脈に対する植え込み型除細動器(ICD)、高齢者の大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療(TAVI)、重症心不全に対するIMPELLA(インペラ)留置など先進的な治療も積極的に導入しています。
2024年12月からは心房細動による脳卒中を予防する経皮的左心耳閉鎖術を開始致しました。
主な疾患・診療内容
虚血性心疾患
急性心筋梗塞・不安定狭心症といった急性冠症候群の救急患者さんは、基本的に全例受け入れの方針をとっています。急性心筋梗塞の入院患者数は、毎年約150人で、そのほとんどに緊急カテーテル治療を施行しています。緊急カテーテル治療を施行した場合の死亡率は過去5年間の平均で4.0%でした。安定狭心症に関しては病状に応じてまず心エコー、運動負荷心電図、負荷心筋シンチ、ホルター心電図などを行いますが、ガイドラインに沿って冠動脈造影検査も積極的に行っています。冠動脈造影CTは2024年度689件、カテーテルによる冠動脈検査は578件でした。
経皮的冠動脈インターベンション(PCI)
緊急治療を含めて毎年400-450件/年のPCIを施行しています。新しいタイプの再狭窄抑制型冠動脈ステントの使用が中心となり、以前に懸念された「再狭窄」、「血栓閉塞」の問題はかなり解消されてきています。それでも再狭窄を生じた場合には、主にカッティングバルーンで拡張した後に薬剤溶出型バルーンなどスコアリングバルーンで治療します。
ロータブレーター、ダイアモンドバック
高度な石灰化を伴う冠動脈狭窄があってバルーンカテーテルによる拡張が困難な場合に病変部を削る器具です。施設認定が必要で限られた施設でしか実施できません。当院では2024年度の実施はロータブレーター30例、ダイアモンドバック6例でした。また、2023年より石灰化病変に対する新規治療デバイスである血管内破砕術(Intravascular Lithotripsy; IVL)を導入し、より複雑な冠動脈病変にも対応可能となっています。2024年度は33例に使用しました。
不整脈
24時間ホルター心電図、長時間ホルター心電図、心エコー、トレッドミル検査、加算平均心電図、あるいはカテーテルによる電気生理学的検査にて不整脈評価を行います。不整脈の種類や重症度に応じて、薬物治療や非薬物治療(カテーテルアブレーション、ペースメーカー、植え込み型除細動器付ペースメーカー)の可否を決定していきます。
カテーテルアブレーション
頻脈性不整脈(発作性上室性頻拍・心房粗動・発作性心房細動、心室頻拍など)に対するカテーテル手術(カテーテルアブレーション)を毎年600件程度実施しており、その3/4は心房細動に対する治療となっています。各種3Dマッピングシステム、高周波アブレーション、局所を冷却するクライオアブレーションシステムまたはパルスフィールドアブレーションにて、患者さんの被曝を軽減しつつ短時間で安全な手技を心がけています。
ペースメーカー植込み
徐脈性不整脈に対してはガイドラインに従って永久ペースメーカー植え込みを行います。可能な限りMRI撮影に対応している機種を選択しています。自宅に居ながら病院でペースメーカーの状態が把握できる遠隔モニタリングシステムを導入しています。高齢の方の一時的な徐脈の場合にはリード(電線)のないリードレスペースメーカーの植え込みも行っています。
植え込み型ループレコーダー(ILR)
原因不明の失神や失神前駆症状の訴えがあっても、通常の診断方法では検出できなかった不整脈を記録する機器です。体表面に植え込み後約3年間作動します。
植え込み型除細動器
心室細動などの致死的頻脈性不整脈から蘇生された場合や、アブレーション治療では根治不可能で突然死の可能性をはらんだ心室頻拍に対しては、植え込み型除細動器(ICDまたはCRT-D)の治療を行っています。本体とリードが心臓や血管に触れない完全皮下植え込み型除細動器(S-ICD)も導入しています。以前のICD植え込み部分が感染を起こした場合やICD植え込みが迷われる場合には着用型自動除細動器(WCD)を最長3か月間装着し経過を見ます。
心不全
心臓超音波検査、冠動脈造影、左室造影、右心カテーテル検査、心筋生検、心臓核医学検査などにより心不全の原因を検索します。内科的治療に抵抗性の重症心不全に対しては非薬物治療の適応を決定します。
両室ペーシング治療
重症慢性心不全でQRS幅の広い左脚ブロック型心電図を呈する症例に対してCRTまたはCRT-Dの植え込みを行っています。
PCPS・脳低体温療法
左主幹部急性心筋梗塞・劇症型心筋炎などの重症急性心不全や電気的除細動不応の重症不整脈には経皮的人工心肺補助装置(PCPS)・脳低体温療法を用いて救命しています。PCPSは2024年度に24例実施しました。また、2021年より経皮的補助人工装置(インペラ)の使用が可能となり、2024年度は11例実施しました。
弁膜症
経胸壁心エコーでのスクリーニング検査の後、必要に応じて経食道心エコーでの精査を行い、心臓血管外科医を交えたハートチームでのカンファレンスで手術適応を検討します。
経食道心エコー
心臓弁膜症で手術を検討しているような場合には、より精密に弁機能を評価するために必須の検査です。心内血栓の検索、感染性心内膜炎の確定診断、先天性心疾患の診断などにも有用です。検査時には静脈麻酔を用いて検査を安楽に受けて頂ける配慮をしています。2024年度は320例の実績があります。
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)
高齢者や他の併存疾患を持っているなど、手術リスクの高い重症大動脈弁狭窄症の患者さんが適応となります。心臓血管外科、麻酔科との合同チームで2024年度には51例実施し、高齢化に伴い近年増加傾向です。
心臓リハビリ
循環器内科・心臓血管外科に入院され薬物治療や手術治療を受けた患者さんが、入院中の心臓リハビリテーションを経て退院した後、引き続いて外来でも心臓リハビリテーションを実施しています。退院後5カ月後まで実施可能です。
その他
薬剤負荷心エコー、運動負荷心エコー
虚血性心疾患では虚血の判定や心筋viability評価の目的で、弁膜症では重症度評価の目的で施行しています。
施設認定
- 日本循環器病学会専門医研修施設
- 日本心血管インターベンション学会専門医研修施設
- 日本不整脈学会・日本心電学会認定不整脈専門医研修施設
- 植え込み型除細動器(ICD)植え込み認定施設
- 両心室ペーシング治療認定施設
- ロータブレーター治療認定施設
医療設備
- 2台の心血管撮影専用シネアンギオ撮影装置
- 経皮的人工心肺(PCPS)
- アブレーション高周波発生装置
- 心内電位3次元マッピングイメージングシステム CARTO-UNIVU
- クライオアブレーションシステム
- 64列マルチスライスCT、SPECT、MRI
- 脳低体温療法体温管理システム
ドクターインタビュー
関連ページ
医師紹介
渡邊 純二
わたなべ じゅんじ

役職
所属学会・
資格
- 日本循環器学会専門医
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- ICD(日本環境感染学会推薦)
- ICLSインストラクター
- JMECCインストラクター
- 日本医師会認定産業医
- 長時間労働医師への面接指導実施医師
略歴
- 舌下免疫療法講習会受講修了
- 医療安全管理者オンラインセミナー受講(全国自治体病院協議会)
専門分野
内田 恭寛
うちだ やすひろ
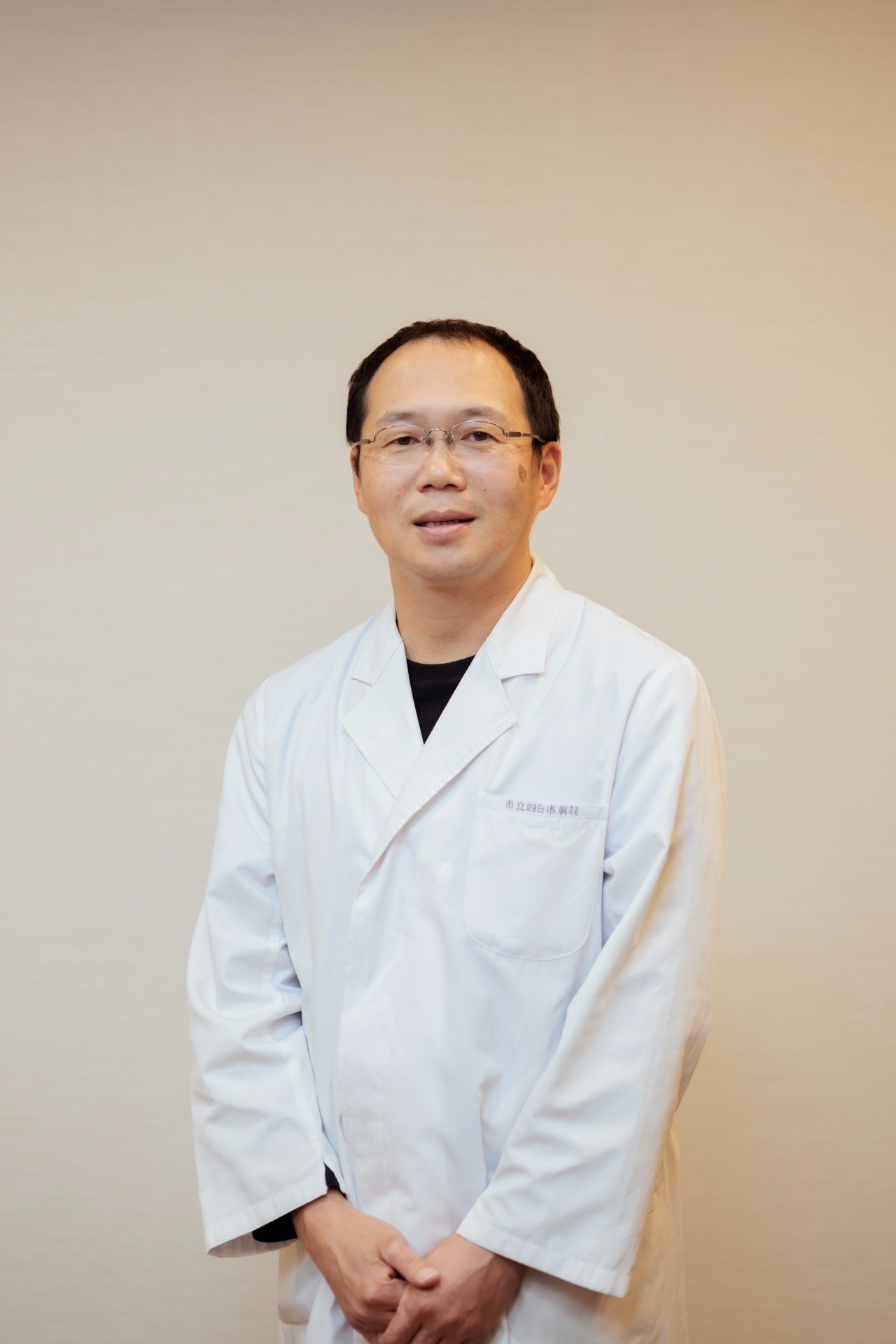
役職
所属学会・
資格
- 日本循環器学会専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会認定医・専門医・代議員
- 経カテーテル的大動脈弁置換術実施医・指導医
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- ICLSインストラクター
- JMECCインストラクター
専門分野
一宮 仁
いちみや ひとし
役職
所属学会・
資格
- 日本内科学会認定内科医
- 日本循環器学会認定循環器専門医
- 日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士
専門分野
水谷 吉晶
みずたに よしあき

役職
所属学会・
資格
- 日本循環器学会専門医
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医
- 日本不整脈心電学会評議員
- 日本不整脈心電学会 着用型除細動器処方医
- 日本不整脈心電学会 リードレスペースメーカー留置資格
- 欧州心臓病学会上級正会員/Fellow of European Society of Cardiology(FESC)
略歴
- 植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療研修終了
専門分野
牧野 裕一朗
まきの ゆういちろう
役職
所属学会・
資格
- 日本循環器学会専門医
- 日本内科学会認定内科医
- 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医
- JB-POT認定
専門分野
野々川 大志
ののかわ だいし
役職
専門分野
渡邊 寛崇
わたなべ ひろたか
役職
所属学会・
資格
- 日本内科学会内科専門医
専門分野
藤原 玄
ふじわら げん
役職
所属学会・
資格
- 日本内科学会認定内科専門医
- 日本心エコー図学会認定SHD心エコー図認証医
- JB-POT認定医
- 日本不整脈心電学会認定植込み型心臓不整脈デバイス認定士
- 日本循環器学会認定循環器専門医
略歴
- 植込み型除細動器(ICD)/ ペーシングによる心不全治療(CRT)合同研修セミナー修了
専門分野
吉江 達希
よしえ たつき
役職
苗村 孝貴
なむら こうき
役職
一宮 惠
いちみや さとし
役職
所属学会・
資格
- 日本循環器学会専門医
- 日本内科学会認定内科医・日本内科学会指導医
- 日本医師会認定産業医
専門分野
金城 昌明
かなしろ まさあき
所属学会・
資格
- 日本循環器学会専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会名誉専門医・認定医
- 日本内科学会認定内科医・内科学会指導医
- 日本医師会認定産業医
- 医療安全管理者
略歴
- 植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療研修修了
専門分野
外来診察予定表
外来診察予定表
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
渡辺(寛) 野々川 |
牧野 |
藤原(交代) 吉江(交代) 苗村(交代) 渡邊副院長 青山 |
渡辺(寛) 野々川 |
牧野 藤原 |
| 午後 |
渡辺(寛) 野々川 |
牧野 一宮 仁 |
藤原(交代) 吉江(交代) 苗村(交代) 渡邊副院長 不整脈外来(水谷(吉))※1 |
ペースメーカー (第1,3週目) |
特殊外来 ペースメーカー外来 第2・第4金曜日 午後
特殊外来 ICD外来 3ヶ月毎 金曜日 午後
※1 不整脈外来は、循環器内科を受診時に予約をお取りします。
診療実績
2024年度
| 急性心筋梗塞患者数 | 129 |
|---|---|
| 心不全入院患者数 |
321 |
| 急性大動脈解離患者数 | 80 |
| 冠動脈造影検査件数 | 578 |
| PCI件数 | 418 |
| 緊急PCI件数 | 149 |
| 待機的PCI件数 | 269 |
| Rotational atherectomy症例数 | 30 |
| Orbital atherectomy症例数 | 6 |
| IVL症例数 | 33 |
| カテーテルアブレーション件数 | 612 |
| 心房細動 | 480 |
| 内Balloonによる | 232 |
| 内RFによる | 95 |
| 内PFAによる | 153 |
| その他 | 132 |
| TAVI件数 | 51 |
| IABP件数 | 50 |
| PCPS件数 | 24 |
| IMPELLA件数 | 11 |
| ペースメーカー植え込み件数 | 97 |
| 新規 | 47 |
| 交換 | 50 |
| リードレスペースメーカー植え込み件数 | 69 |
| ICD植え込み件数 | 26 |
| 新規 | 10 |
| 交換 | 16 |
| CRT/CRT-D件数 | 10 |
| 冠動脈CT件数 | 689 |
| 負荷心筋血流シンチ件数 | 104 |
| 心臓MRI件数 | 58 |
| 経胸壁心エコー件数 | 8650 |
| 経食道心エコー件数 | 320 |
| 運動負荷心電図件数 | 313 |
| CPX件数 | 22 |
| ホルター心電図件数 | 2211 |
- 不整脈に対するカテーテルアブレーション治療が著しく増加しています。不整脈分野での新しい取り組みとしては、植え込み型ループレコーダー (ILR)、完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)、着用型自動除細動器(WCD)、パルスフィールドアブレーション、リードレスペースメーカーなどが挙げられます。
- 虚血性心疾患に対するカテーテル治療も400-450件/年で推移しています。方向性冠動脈粥腫切除術(DCA)、Rotablator、Diamondback、Shockwaveなど用いてComplex PCIにも引き続き取り組んでいます。
- 心臓血管外科と共同で実施しているTAVI(経カテーテル的大動脈弁植込み術)も順調です。
